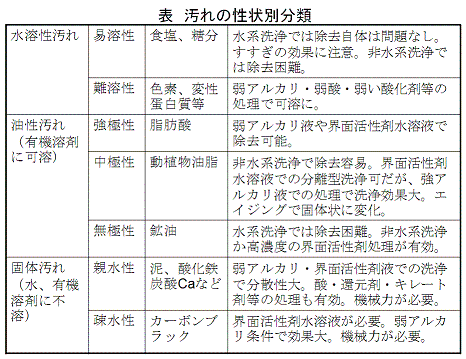
汚れとは、本来はそこに存在することが望ましくなく、除去することが求められる物質を指す。その汚れを除去する操作が洗浄である。この洗浄を科学的に考察する場合の第一歩は、やはり汚れとはどういうものかを整理すること、すなわち汚れを性状別に分類することである。特殊な目的から細菌汚れ、放射能汚れなどとして区別される場合もあるが、ここでは洗浄理論の基礎となる性状別の分類法について説明する。
一般的には汚れは水溶性汚れ、油溶性汚れ、固体汚れの3種に分けられる。更に、水溶性汚れは易溶性汚れと難溶性汚れに、油溶性汚れは強極性汚れ、中極性汚れ、無極性汚れ、固体汚れは親水性汚れと親油性汚れに分けて考えられる。
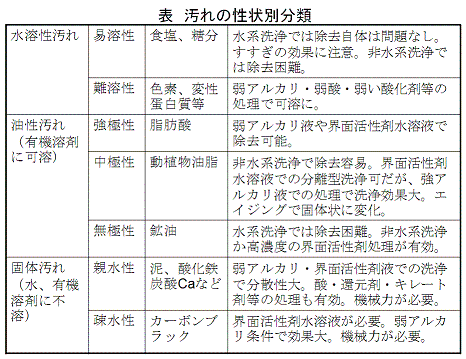
【水溶性汚れ】
汚れの中でも水に溶解する汚れを水溶性汚れと呼ぶ。但し、水に接触すると簡単に溶解する汚れもあれば、水に何らかの薬剤を加えることによって溶解することができる汚れもある。前者を易溶性汚れ、後者を難溶性汚れとして区別する。食塩、砂糖などは水と接触させると簡単に溶解する易溶性汚れである。また汗をかいた場合、その汗が乾いていない状況では水洗いで容易に除去することができ、これも易溶性汚れに分類される。易溶性汚れを除去するためには、基本的に洗剤は必要ない。大量の水で洗い流せば容易に除去できる。但し、食塩や砂糖などが簡単に除去できるのは水で洗う場合に限られる。水とは全く異なる性質、すなわち油の性質を有した液体であるベンジン等の有機溶剤では、これらの水に易溶性の汚れはかえって除去し難い汚れになる。難溶性汚れは、水に接触させるのみでは除去が困難だが、弱アルカリや弱い酸化剤などの薬剤を用いると溶解できる。例えば、やや変性した蛋白質汚れは、アルカリ、酸素系漂白剤、タンパク質分解酵素等を作用させると溶解できるようになる。汗汚れも、新しいものは水洗いで容易に除去できるが、古くなったものは漂白剤等を利用しないと溶解しにくくなる。
【油溶性汚れ】
油性の性質をもった有機溶剤には溶解するが、水には溶解しない性質の汚れを油溶性汚れと呼ぶ。有機溶剤には、一般のしみ抜きに用いるベンジン、アルコール(エタノール)のほか、クロロホルム、ジエチルエーテル(通称:エーテル)、石油ベンジン、石油エーテル、ベンゼン、トルエン、キシレンなどが挙げられる。また、油性汚れの中でも極性の有無によって性質を分けることができる。極性が高いものは界面活性剤水溶液で比較的容易に除去できるが、極性のないものは水系の洗浄システムでは除去が困難であり、有機溶剤を用いたドライクリーニングやしみ抜き等で除去が可能になる。極性の高い油性汚れの代表は脂肪酸である。牛脂、豚脂、オリーブオイル、サラダ油、てんぷら油等は油脂や中性脂肪と呼ばれる物質で、トリグリセリドと呼ばれる中程度の極性を有した物質である。無極性の油汚れとは、機械油等に用いられる鉱油等の炭化水素汚れが代表的でありる。無極性油の中の、特に粘度の高い汚れは一般の界面活性剤水溶液ではなかなか対応しがたい汚れとなる。
【固体汚れ】
水にも溶解せず、油性の有機溶剤等にも溶解しない汚れを固体汚れと呼ぶ。特に粒子状の汚れは固体粒子汚れとよびます。固体汚れは、また親水性固体汚れと親油性(疎水性)固体汚れに分類できる。水中に混ぜようとした際に、容易に水と混ざり合うのが親水性固体汚れであり、水には混ざり合いにくい油性の性質を有した固体汚れが親油性固体汚れとなる。親水性固体汚れの代表格は泥である。泥の主成分はケイ素を主体とした成分であるが、有色成分は鉄分等が主体となっている。洗浄試験ではモデル汚れとして酸化鉄を用いたりする。親水性なので水洗いでも機械力をうまく利用すれば除去が可能であるが、界面活性剤の作用で除去性は高まる。疎水性固体汚れの代表はススである。ススは有機物を酸素の不足した状態で燃焼すると発生する炭素主体の黒色粒子で、これを工業的に製造したものがカーボンブラックである。ススやカーボンブラックは疎水性なので水とは非常に混ざり合いにくく、水系洗浄のためには界面活性剤の利用が欠かせない。固体汚れの特徴は、機械力がなければ基本的に除去ができないという点であり、界面活性剤等の洗剤の成分はその機械力の作用を効率的に生かすという程度の意味しかない。いかに効率的な機械力を作用させるかが固体汚れの洗浄における課題となる。
(2009.1.15)
⇒「洗浄・洗剤の科学」トップページへ